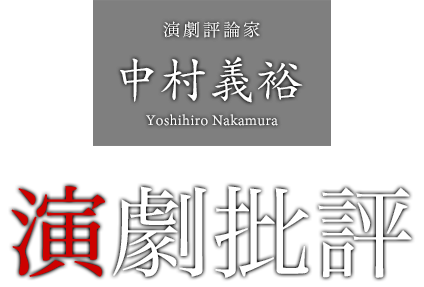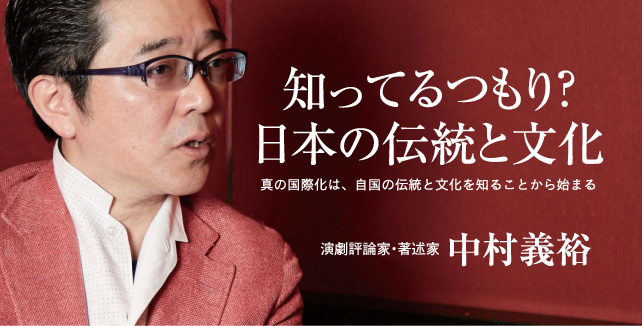国立劇場の開場五十周年を記念して、十月から十二月までの三か月をかけて、歌舞伎の三大名作の一つ『仮名手本忠臣蔵』を完全に近い形で通して上演するという、壮大なプロジェクトだ。今から三十年前の昭和六十一年、開場二十周年記念の折にも同様の公演が行われ、当時、昭和の歌舞伎を牽引して来た大幹部の名優たちが揃って演じた。今回は、その折よりも原作に近い上演形態で、平成の歌舞伎を牽引して来た円熟の役者から花形までが顔を揃え、月ごとに配役を変えながらの上演である。
十月は、長い物語の荘重な始まり『大序』から、ふだんは滅多に上演されない『二段目』、松の廊下の刃傷で有名な『三段目』、判官切腹の『四段目』までの上演である。それでも、二回の休憩を挟んで上演時間が五時間十五分、「忠臣蔵」いかに長大な物語であるかがわかるというものだ。最近は、『忠臣蔵』のエピソード自体が徐々に我々庶民の一般教養から遠くなりつつある時代とも言える。「忠義」という感情が理解も実感もできない中で、芝居の中だけでもその感覚を味わい、江戸時代の人々の感覚に同調できる、それが歌舞伎の魅力の一つでもある。
幕開き前に、忠臣蔵ならではの「口上人形」が出て、配役を発表し、荘重に幕が開く。『大序』、兜改めの場は、中村梅玉の塩谷判官、片岡秀太郎の顔世御前、市川左團次の高師直、中村松江の足利直義、中村錦之助の桃井若狭之助。梅玉の判官にはやはり気品があり、この役の持つ味わいや後の悲劇の予兆を感じさせる儚さも持ち合わせている。左團次の師直は、今はこの人しかあるまい、という役どころで、特に『三段目』まで、憎々しさと狡さの限りを見せる。顔世御前は片岡秀太郎。塩谷の奥方、という気品がある。実は、秀太郎は三十年前の公演には由良之助の息子・力弥で出演しており、当時の主なメンバーの中では唯一健在の役者だ。伝統を継承し続けてきた歌舞伎の「重さ」を感じる。
続いて『二段目』。ふだんは全く上演されない場面で、私も三十年ぶりになる。しかし、前回の上演では「建長寺」となっており、今回は原作通り「桃井館」での上演である。血気に逸る若狭之助、それを諫める市川團蔵の家老・加古川本蔵とのやり取りだ。落ち着いた芝居で錦之を受ける團蔵、渋い役ながら年功を感じる。隼人の力弥と中村米吉の淡い恋模様が描かれる場面もあり、この場の隼人は健闘。
『三段目』。最初は「足利館門前」で、師直の家来・鷺坂伴内が坂東橘太郎。子役時代は「坂東うさぎ」の名で身の軽さを見せていたが、門閥外から歌舞伎の世界へ入り、修行を重ねれば、こういう役もできるのだ、とこれから歌舞伎を目指す人への目標でもある。滑稽な味を軽妙に生かし、家来とのやり取りが秀逸だ。
いよいよ「松の間」、刃傷の場面となる。左團次の師直が「これでもか」と言わんばかりに梅玉の判官をいたぶり、追い詰めてゆく様子が絶妙だ。とうとう堪えかね、一気に感情がせき上げて刀を抜く梅玉。危うく保たれていた「動」と「静」の均衡が、破れる瞬間に緊張感がある。第一部での最初の見せ場であり、これからの悲劇の始まりになる場面だ。「裏門」は市川高麗蔵のおかると中村扇雀の早野勘平が密会をしており、勘平が殿の大事に居合わせることができなかったことを悔やむ。申し訳なさに自害しようとする勘平を止めるおかる。扇雀がいささか生彩を欠いていたように見えたのが残念だ。
第一部の終わりで、『忠臣蔵』の中でも重要な『四段目』。悲劇の後、判官を慰めようと、顔世が花を活けて判官に贈ろうとする「花献上」から始まる。特にこう、という場面ではないが、「通し上演」という性質上、必要なことだ。悲劇を予感していても、武士のたしなみは忘れぬ、という心情がわかる。
そして「判官切腹」。ロビーに貼り紙があり、「昔にならい通さん場とする」旨が書いてある。これにはいささかの解説が必要であろう。江戸時代の芝居小屋は今よりも自由度が高く、上演中でも劇場に隣接する芝居茶屋から弁当や菓子などの『出前』が届いた。しかし、判官切腹のこの場面だけは出入り禁止で、「通さん場」との名称が付いたのだ。今回は、それにならい、「判官切腹」の場面は出入り禁止としたわけだ。ついでに言えば、同じく江戸時代は、塩谷判官を演じた役者は、切腹の場面が終わると、ひっそりと駕籠で帰宅した、という話がある。芝居が終わって楽屋で元気な顔をしていたのでは興ざめ、というところだろう。単なる裏話ではなく、270年近く、こうした工夫や伝承が積み重ねられて来たのが『忠臣蔵』という作品だ、ということだ。
さて、「判官切腹」。家老の大星由良之助の到着を待ち兼ねる判官は、小姓の力弥に様子を見に行かせるが、「まだ着かない」とのこと。この場の隼人の力弥、『二段目』に比べて良くない。これは、同じ役でも『二段目』は美しさと若々しさで演じられても、『四段目』になるとそれ以上の重みを求められる、ということだ。これから経験を重ねてゆく年代だけに、よい経験だと思う。この場の隼人には「危うい魅力」がある。検視の役人は、石堂に左團次、薬師寺が坂東彦三郎。左團次は今月二役だが、こちらは気が変わって白塗りで情に篤い役だ。梅玉の判官は、ぴたりと役に納まる仁を持っており、安心して観ていられる。短慮の上のこととは言え、「大名」が起こした事件でなくてはならない。そのことを、しっかりと、胸に刻ませる判官だ。
判官が諦めて刀を突き立てた瞬間、幸四郎の由良之助が出る。まずはその風格、立派な由良之助だ。横顔などは、亡父・白鸚を彷彿とさせる。ただ、風貌は似ていても、ここにいるのは九代目幸四郎の由良之助だ。判官との間で、交わす言葉は少なくとも、お互いの心を汲み取る信頼感と情愛というものが、胸に伝わって来る。そして、城を明け渡し、決意を固めるべく一歩一歩、怒りと哀しみが交錯がしながら歩みを進める。これぞ、まさに平成の由良之助だ。城を枕に討ち死に、と逸る侍たちを納め、「まだご料簡が若い、若い」とたしなめる辺りの堂々たる見事さと朗々とした科白は、『四段目』の最後にふさわしい。いったん幕が閉まり、三味線の「三重」」に送られて花道を引っ込む由良之助の姿は、江戸と現在をつなぐ感情でもある。『仮名手本忠臣蔵 四段目』という、歌舞伎の演目の中でも大きな位置を占めるこの幕切れの幸四郎、圧巻である。
この壮大なドラマに含まれている多くの人々の感情が、現代の観客にもきちんと通用することを知らせた効果は大きい。十一月、十二月の「第二部」「第三部」がどんなドラマを見せてくれるのか、秋の大きな話題になりそうだ。