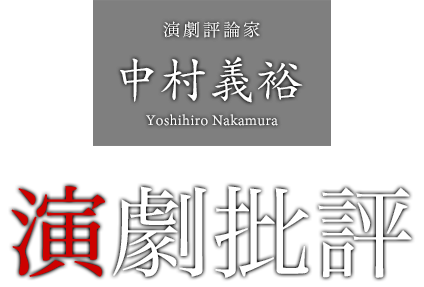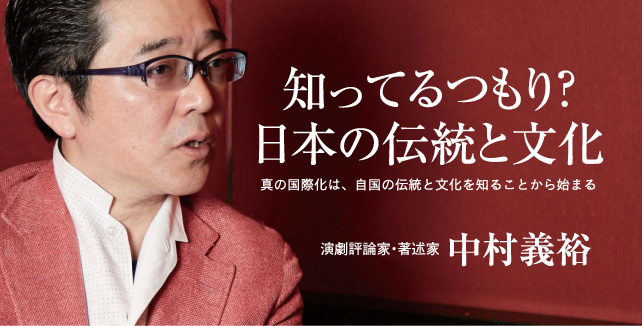十月の名古屋・顔見世興行の昼の部は、坂東彌十郎の弁慶、大谷廣太郎の従者、中村萬太郎の牛若丸による『橋弁慶』で幕を開ける。彌十郎を上置きに据えて若手たちの修行の場、という形だが、30分に満たない踊りでも、長唄に乗っての弁慶との立ち回りに、のちに御大将になる牛若丸の優美さとしなやかな勁さを見せなくてはならない。二人の若手にとっては、よい勉強の場だ。
次が、染五郎の沢市、孝太郎のお里で『壺坂霊験記』。関西では馴染み深い「壷坂寺」の奇跡を描いた作品で、成り立ちが珍しく、明治期になって人形浄瑠璃の大夫によって作られた作品だ。お里の心理の述懐とも言うべき「三つ違いの兄さんと」のくだりで夫婦の情愛を感じさせ、しかも登場人物はこの夫婦のみ(最後に観世音菩薩が登場するが、わずかな時間である)で一幕三場の芝居をもたせなくてはならない。原作では幕開きに村の人々が数人登場するが、今回はこの部分はカットしての上演だ。上方産の芝居で舞台も上方だけに、義太夫の節回しが身体に染み付いてなくてはなかなか難しい。また、主役の沢市が盲人であるということも相まってか、最近はあまり上演の機会がないが、昭和の中頃までは、お里のクドキが人の口の端にのぼるほど、身近な芝居でもあった。
盲目の身で、たださえ不自由な日々をかこつ沢市。恋女房のお里は、毎夜どこかへ忍んでゆく。それが、他に男ができたのでは、と懊悩する沢市に、お里は壺坂の観音様へ、沢市の眼が開くように、毎夜祈願に出かけていたことがわかり、二人で詣でることにする。しかし、世をはかなんだ沢市は、谷底へ身投げをしてしまう。それが、観音様の霊力で蘇生し、眼も見えるようになる、というまさに「霊験」の話だ。
染五郎の沢市と孝太郎のお里が良いコンビなのは、年齢が近いというだけのものではない。二人とも、幼い頃から歌舞伎の古典の勉強を続けて来た共通項は大きいだろう。40代になって過去の蓄積が花開くほどに時間のかかる芸能が歌舞伎なのだ。今、歌舞伎の若手の役者たちがマスコミへいろいろな形で露出をするのは悪いことではない。しかし、歌舞伎の土台を固める重要な時期でもあることを忘れてはほしくない。
孝太郎のお里は、夜の部の『寺子屋』の千代よりも遥かに若返り、甲斐甲斐しく沢市に尽くす世話女房ぶりがいい。上方の役者であり、東西のやり方に通じた父・仁左衛門の薫陶だろうか、危なげのないお里だ。相手役を立てる女形の「距離感」が自然なのも好ましい。染五郎の沢市、懊悩をよく表現しているが、上方狂言の難しさに、苦労が見える。しかし、だんだん上演頻度が少なくなる芝居をこうして残そうという意気込みは買いたいものだ。
最後は『ぢいさんばあさん』で、森鴎外の短編小説を宇野信夫が歌舞伎化した作品。仁左衛門の美濃部伊織と時蔵のるんという若夫婦が、伊織の京への単身赴任で離ればなれになる。その間に、伊織は京でふとしたことで同僚を斬り殺してしまい、その咎で配流となるが、罪を許され、二人が若き日々を過ごした江戸の邸宅で、三十七年ぶりに落ち合うという物語だ。美男美女のカップルが終幕で老夫婦になって再会するのがこの芝居のミソで、そこに作者・宇野信夫の詩情が漂う作品だ。
仁左衛門の若々しさに目を見張るのが第一で、「ぢいさん」になってからもコミカルな動きで前半の悲劇をハッピーエンドに変える。時蔵のるんは、老女になってからの気品と貫禄たっぷりの様子がいい。こうした芝居の嘘をそのまま観客に納得させてしまうのがベテランの腕だろう。佳品、である。
少し時代を遡れば、よい二番目狂言が残されている。この作品は上演頻度が高い方だが、振り返って前へ進むことも、今の歌舞伎の宿題の一つなのかもしれない。